初めてのGlastonbury Festival DAY6〈完〉

初めてGlastonbury Festivalを体験したオルグスタッフの現地レポート。最終回は、6日目の出来事と振り返りをまとめてお届けします。(DAY1はこちらから)
グラストという街

グラスト6日目。ついに最終日を迎えた。連日朝方まで遊び回っているが、不思議なくらい疲労感はない。楽しさが疲れを凌駕しているのだろう。
体力が続いているのは、天気のおかげもある。毎日30度近い暑さが続いているものの、ずぶ濡れになるような雨には降られていない。雨に打たれ、足元が泥だらけになっていたら、気力も体力も削られているはずだ。1人用のテントには服を干すスペースもないので、雨からのリカバリーは考えるだけで憂鬱になる。
最終日も天気予報は晴れ。不安要素がないと、リソースはすべて楽しむことに向けられる。

5日間かけて会場のほとんどのエリアに足を運んだ。しかし、すべてのステージやお店に行けたわけではない。
ステージは、オフィシャルプログラムに記載のない場所も多い。昨日まであったのに今日はなくなっているステージや、道端でゲリラ的にライブが行われることもあって、とてもではないが追いきれない。はじめはすべてを回るつもりで意気込んでいたが、実際に歩いてみてそれが無謀な目標であることに気がついた。

お店のバリエーションも実に多種多様だ。世界各国の料理(日本のラーメンや寿司もあった)やスーパー、モバイルショップにキャンプ用品のお店まである。
テントも服も食べ物も現地で買えるので、お金さえあれば手ぶらで会場に来てもなんとかなってしまう。お店の数や種類でいえば、自分が暮らす街よりも充実しているかもしれない。

バーはもちろんのこと、映画館や遊園地、サウナなんかもあって、街歩きの感覚で巡っていても飽きることはない。実際、ライブは見ずにグラストの雰囲気を楽しみに来ているという人とも出会った。もはや、ここはひとつの街だ。「旅行先としてのグラスト」という選択も十分にあり得る。

日本のフェスと比べると、年配の参加者も目立つ。足の先から帽子までスパンコールの衣装でコーディネートしたおばあさんや、電動カートで遊びに来ているおじいさんも珍しくなくて、まさに年齢など関係ないといった感じだ。

日本のフェスとの違いで言うと、ファッションのことも印象的だった。日本では機能性を重視したアウトドアウェアの人が多いけれど、グラストではほとんど見かけない。Tシャツに短パン、スニーカー、女性はワンピースなど、街中と変わらないような格好の人がほとんどだ。

夜にはドレスアップして遊びに出かける人もたくさんいて、芝の上のフロアは出会いの場にもなっている。
視線を飛ばし、声をかけ、酒を飲み交わす。音楽やダンスだけでなく、出会いを求めて遊びに繰り出したって構わない。どれだけたくさんの人がいても、それぞれがそれぞれの楽しみ方をしているのがいいなと思う。
退屈を愉快な時間に変える音楽の力

最終日もたくさんの素晴らしいライブを体験した。レジェンド枠のロッド・スチュワートは80歳とは思えないパワフルなステージでピラミッドを埋め尽くした大観衆を魅了(全日程を通して一番の客入りだったのではないだろうか?)。ゲストとしてローリング・ストーンズのロン・ウッドも登場し、オールタイムベストなセットリストで名曲を惜しみなく披露してくれた。

去年のフジロックにも出演したガール・イン・レッドは、パークステージに登場。開放的な雰囲気のステージに、オーディエンスのシンガロングを伴ったカラフルなサウンドが鳴り響く。野外コンサートの原風景として、額に入れて飾りたいくらいの美しい光景だった。

アザーステージのトリを務めたのはプロディジー。ステージから放たれるアグレッシブな音と光は、空が暗くなっていくごとに鋭さを増していく。最前線では無数の発煙筒が焚かれ、もうもうと立ちこめる煙越しに見るライブは自分がグラストにいることを強烈に感じさせてくれた。

音楽の力を感じたのはステージだけではない。会場を東西に横切るレールウェイという道では、スタッフと客による大合唱が起こる場面もあった。
主要ステージのライブが終わると大勢の人がシャングリラ方面に流れるため、混雑緩和のために交通規制が行われる。一時的にゲートを閉じて、人の流れを調整するのだ。客としては足止めされることにヤキモキする状況だが、スタッフの人たちはフレンドリーな姿勢を崩さない。それどころかメガホンでオアシスの“Don’t look back in anger”を歌い始めたではないか。
それに合わせて待っている客が1人、また1人と歌に加わっていく。その輪がどんどんと広がり、夜中のレールウェイで大合唱が起こった。この状況を楽しい時間にしようとするスタッフも、そこに迷わず乗っていく客の姿勢もすごい。曲が歌い終わったタイミングでゲートが開けられ、客はスタッフとハイタッチをしながらテンション高く奥地へ流れていった。

場合によってはピリピリするような状況も、ユーモアとアイデアで愉快な時間に変えられる。スタッフも客も、この場を楽しもうとする共通の姿勢が、こうした光景を生むのだろう。音楽にはそういう力があるというのを、まざまざと見せつけられる場面だった。
フェスティバルとは何なのか?

グラストの会場では至るところで「have a great festival!」という声がかけられる。最初は特に意識することなく聞いていたが、ふと「フェスティバルとは何なんだろう?」と思った。少なくとも、その言葉が指しているのはライブのことだけではないはずだ。

グラストに来て感じるのは、ここには「誰もが好きに過ごしていい」という安心感があることだ。どんな服装をしても、どんな主張を持っていても、どんなふうに過ごしてもいい。それを誰かに否定される筋合いはない。
自分が自由であるために、誰かの自由を脅かさない。そういう空気感が安心に繋がっているのだろう。だからこそ、多様な人、多様なコンテンツが同居できているのだと思う。誰かの意図に沿って作られたものではなく、それぞれが自由に過ごした結果として形になるもの。それがフェスティバルなのではないかと感じた。

最終日の仕事を終えて、毎日荷物を預かってもらっていたロックアップのテントにお礼を伝えに行く。いつも顔を合わせていたスタッフの方に「初めてのグラストはどうだった?」と聞かれ、「未知の体験ばかりでエキサイティングだった!」と答えると、「そうだろ。ここはアナザーワールドだからね」と言われた。
何十年も通っているグラストのことを「年に一度の心の洗濯」と表現する人もいた。今なら少しわかる。ここには異世界にも思える自由さと寛容さがあり、同時に普段からもっと自分らしく生きていいのだと思い出させてくれる場所なのだと思う。

グラストにいる間、目の前で起こるあらゆることに心と体が反応して生きている心地がした。こんなにもみずみずしい感覚でいられるのかと、自分でも嬉しくなるほどだった。それはきっと会場を出た瞬間に失われるものではないし、現実社会にも持って帰れる感覚だと思う。
人の目や社会的な評価に捉われてしまうことはあるけれど、本当はもっと自由でいいし、自分の主張を大切にしていい。そのことを忘れそうになったら、誰の目も気にせず、自分の興味に従って、好きなように過ごしたグラストでの日々のことを思い出そう。
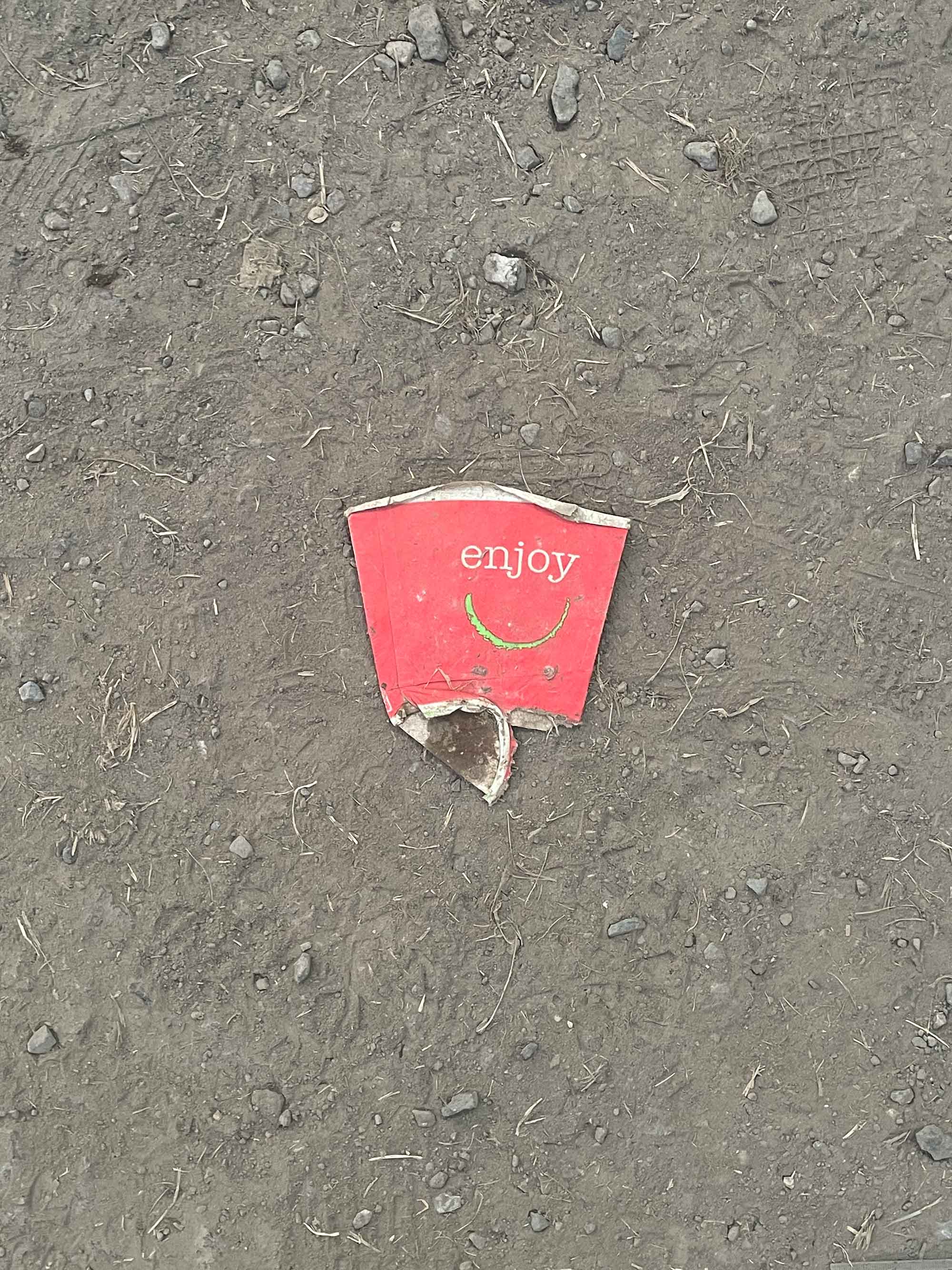
いつか行きたいと思っていた憧れのグラスト。ここでの体験が自分の人生にどんな影響を与えてくれるのか、日本に戻ってからの日々も楽しみだ。本当にあっという間の6日間だった。また必ず戻って来たいと思う。
・初めてのGlastonbury Festival DAY1
・初めてのGlastonbury Festival DAY2
・初めてのGlastonbury Festival DAY3
・初めてのGlastonbury Festival DAY4
・初めてのGlastonbury Festival DAY5
・初めてのGlastonbury Festival DAY6〈完〉
文章:阿部光平(https://x.com/Fu_HEY)




